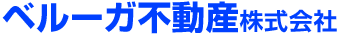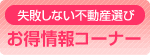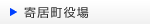�`�[�J�s�[�J���w�Z�O�`�@�u�x���[�K�s���Y������Ёv
�@2014�N08��02��
<No 26>
�����s���Ȃ��s���Y�I�сE�E�W�����`�������ꂽ�_�����̎����̈łɂ��ā`
���s���Ȃ��s���Y�I�сE�E
�W�����̃e�[�}�u�������ꂽ�_�����̎����̈łɂ��āv
�����Q�U�N�S���P�����͂����͂T�Q�~�ɕ����͂W�O�~���W�Q�~�ɗX�֗�����
��������܂������A�ŋ߂ɂȂ��āu���A�͂����͂T�Q�~�H�v�ƋC�t���ꂽ����
���\������̂ł́H�Ǝv���܂��B���ł̕ω������̊������u����Łv
�Ƃ͈���āA�X�֗����͏�����������N���̎����ɂȂ�Ȃ��Ɓu���������v
�̎������킩�Ȃ���������܂���B
�Ƃ���ŁA�u�Łv�͍���S���P�����u�ꕔ���������v���Ă���܂��B
�����͈ꕔ�����������܂����łɂ��ď������b�����܂��B
����u�s���Y�̏��n�Ɋւ���_���̈Ŋz�v���Ⴆ�Εs���Y�̏��n�z��
�T�O�O���~���P�O�O�O���~�ȉ��̏ꍇ�͉����O�͂P�O�C�O�O�O�~�̎�����
�_�ɓ\��܂������A�S���P���ȍ~�͂T�C�O�O�O�~�Ɖ�������܂����B
�P�O�O�O���~���T�O�O�O���~�ȉ��̏ꍇ�͂P�T�C�O�O�O�~����P�O�C�O�O�O�~
�ɂȂ��Ă���܂��B�i�����z�H���̐����Ɋւ���_�̈Ŋz���S���P��
���ύX����Ă���܂��B�E�E�ڍׂɂ��܂��Ă͌��I�Ȏ����������Q�l�肢
�܂��B�j
��������łt�o�ɂƂ��Ȃ��u�ł̌��z�v��u�Z�܂��̋��t�����x�v�̐V��
�ȂǁA���Ŋ��̊ɘa�Ή��ɋꗶ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���Ɓu�Łv�ɂ��Ă͗̎����Ɉ�\��`���̂���u���Ǝҁv���ɂƂ�
�܂��Ă������O�͂R�O�C�O�O�O�~��������ېł������̂��T�O�C�O�O�O�~����
�܂Ŏ�����\��Ȃ��Ă悢��ېŘg���g�債�Ă���܂��B
(�X�[�c���̔̔��X�̏ꍇ�͂��Ȃ�����̎g�p�ʂ�����̂ł́E�Ǝv���܂��j
�Ō�Ɂu�v�ɂ��Ă̎G�w�I�Ȃ��b���ł����E�E
���{�ł́u�����v�̑��ɂ��@�@���ǂɂē��{�����擾���鎞�ɐ\�����ɓ\��
�u�o�L�v�Ȃǂ��̗p�r�ɍ��킹�ĐF�X�ȁu�v�����s����Ă��܂��B
��ʓI�ɂȂ��݂̔����u�v�Ƃ��Ă͓������ɓ�����o�^���W�̓o�^�\���̍�
�ɐ\�����ɓ\��܂��u�����v������܂��B������N�@���Ђ̃x���[�K�̃��S
�}�[�N�̏��W�o�^��\������ہA�X�ǂɂčw�����Ďn�߂āu�q���v���܂����B
�������I�ɂ��������i�̂���\��́u�v�ł����B�����������̂��������
�u�����v�Ȃǂ��낢��ȁu�v�ɂ��ăC���^�[�l�b�g�Ȃǂʼn摜������
�Ă݂Ă͂������ł��傤���H
�����X�����̃e�[�}�́u�y�n�̐��`�n�ƕό`�n�ɂ��čl���邱�Ɓv��\��ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x���[�K�s���Y(���j�V��
�@2014�N07��01��
<No 27>
�����Q�O�P�S�N�����s���Ȃ��s���Y�I�сE�E�E�V�����` ���X�̓X���ʐ^�Ƒ�Q���ł����킹�����̃L�b�Y�R�[�i�[�̎ʐ^�ł��B


�����̃e�[�}�u���Ã}���V�����̍w���O�`�F�b�N�|�C���g�v�ɂ���
�����́u���Ã}���V�����̍w���\���ݑO�v�ɂ��Њm�F���Ă��������_��
�T�|�C���g�ɍi���Ă��Љ���Ă��������܂��B
���w���\���ݑO�ɂ��炩���ߊm�F�������|�C���g��
�@�w���\��̕������A�u�Z��[�����Łv�̑Ώۂ��ǂ����̊m�F�ɂ��āB
�Z��[���𗘗p���Ă̍w���̏ꍇ�́A�����̔̔��S���҂Ɂu��������Ɓv
�Ώە������ǂ����̊m�F������鎖�������߂��܂��B���Ẫ}���V������
�Q�T�N�ȏ㌚�z���o�߂��������������A���ɒz�N�����Q�T�N���Ă���
�ꍇ�ł��ϐk��Ȃǂ̈��̏��������Ă��邩���u�Z��[�����Łv
�̑Ώە������ǂ����͂�͂�̔��S���҂���u�_��̓����ł͂Ȃ��A�O
�����āv�m�F���Ă����������悢�Ǝv���܂��i�O�����ĕ����Ă���A
���Ƃ��ΏۊO�������Ƃ��Ă��u�Z��[�����ł͊��҂ł��Ȃ��E�E�v����
�S�̏������ł��܂��̂ŁE�E�j
�A���ԏ�̏ꏊ�̋�̓I�Ȋm�F�ɂ��āB
�u���ԏ�͋ߗׂɂā@�������~�v�Ȃǂ̍L���̏ꍇ�͍w���\���ݑO�ɁA
�u���ۂɋߗׂ̂ǂ��̏ꏊ����邱�Ƃ��\���H�v��̔��S���҂�
�K�v�ɉ����āu�����g�Łv�m�F����鎖�������߂��܂��B���ɂQ�䕪�m��
���K�v�ȏꍇ��A���S���^�C�v�̎Ԃ����L�̕��͂����ӊ肢�܂��B
�B����ݒu�̐ݔ��@�퓙�̌o�ߔN���̊m�F�ɂ��āB
�u����ɂĔ��p�v�̏ꍇ�̓K�X��⊷�C��A�����C�̃R���g���[���[�A
�O���Z�҂��g�p���Ă����G�A�R�������A�ݒu�シ�łɉ��N�o�߂��Ă��邩
�J�Ɋm�F��������鎖�������߂��܂��B�ꍇ�ɂ��o�ߔN���ɉ�����
�����J�n�O�Ɂu���啉�S�v�ł����Ă����i�����C����A�V�i����������
���܂������������I�ɂ����ȏꍇ������܂��B�����J�n��͋Ǝ҂��Ă��
�̌��ς��C���A�����͎��ԂƂ����������O����ςł��B���ɃG�A�R��
�͂܂��g����ꍇ�ł��P�Q�N�ȏ�O�̂��̂͌��݂̂��̂ɔ�ׂċ����ق�
�d�C������܂��B���������̊ԁu�����d�C��v���Ă��܂��Ă���
���ǁu�����v�Ƃ����Ƃ������Ƃ��悭����܂��B�����ӊ肢�܂��B
�i�F�����̓��ό��w�̍ہA���ē��҂̋�������������Όg�ѓd�b�̃J����
�ŃG�A�R���ɓ\���Ă���^���v���[�g�̕�����傫���ʂ��Ă����A�K�v
�Ȏ��Ɍォ��N����^���A���[�J�[�����m�F�ł��܂��j
�C�Ǘ��̐��̌��݂̎���̊m�F�ɂ��āB
�u�Ǘ��l���L�v�̃}���V�����ł����Ă��A�V�z���́u�풓�v�������̂Ɍ���
�́E�E�Ƃ����ꍇ������܂��B�P�K�̃��r�[�ɂ���Ǘ��l�����A�����d�C
�������ĕ��Ă���A�u����I�ȏ���̂݁E�E�v�ɊǗ����@���ύX�����
����ꍇ������܂��B���ЁA�̔��S���҂Ɂu����ɂ��āv������������A
�C�ɂȂ�悤�ł�����u�����g�Łv�ēx���n�m�F����Ă͂������ł��傤���B
�E�E�E�u�h�ƃJ�����쓮���I�v�̌f�����G���x�[�^�[�z�[���ɂ������̂�
���S���Ǝv���čw�������߂��̂Ɏ��ۂ́E�E�Ƃ��������s�����w����ɂ���
�Ȃ��悤�C�ɂȂ�_������܂����玖�O�ɔ̔��S���҂ɂ������ɂȂ�A
�u�}���V�����̊Ǘ���Ёv�ɒS���҂����e�m�F�����Ă���������Ǝv��
�܂��B
�D�w���\��̃}���V�����́u�ŐV�̋K��v�̊m�F�ɂ��āB
�w���}���V�����̏ꍇ�͋K��⏅�炷�ׂ����������̃}���V�������ƂɈႢ
�܂��B���Ɂu�y�b�g�Ɠ����v���������̕��́A�K���̔��S���҂Ɂu�K��v
�ɂ��Ċm�F���Ă����������������߂��܂��B�y�b�g�̎���ɂ��Ă̋K��
�́u�V�z�̔����̋K��v�ɂ������ďC���ύX����Ă���ꍇ���悭����܂��B
���O�Ɂu�����������y�b�g�̐��Ǝ�ʁv���\���H�̔��S���҂Ɉ˗�����
�Ǘ���ЂɊm�F�̏�A�w���\���݂����ꂽ�������S���Ǝv���܂��B
*�@���A��N�P�O�����́u���s���Ȃ��E�E�v�̒��ł��}���V�����́u�Ǘ���v
��u�C�U�ϗ����v�̎��ɂ��ď����L�ڂ��Ă���܂��̂ŁA���Ã}���V����
�̍w��������������Ă�����͍�N�̂P�O�����́u���s���Ȃ��s���Y�I�сE�v
�����Ђ��Q�l�肢�܂��B
�����W�����̃e�[�}�́u�������ꂽ�A�_�����̎����̈łɂ��āv
��\��ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x���[�K�s���Y�i���j�@�V��
�@2014�N06��02��
<No 28>
�����Q�O�P�S�N�����s���Ȃ��s���Y�I�сE�E6�����`
�����̃e�[�}�u�_�̏d�v���������͑�ł��v
�����̓e�[�}���炵�Ă�����ƌ��ꂵ�����b�ɂȂ�܂����E�E
�������s���Y�Ǝ҂͕s���Y�̔����_��̒����̑O�A���q�l�ɑ���
�u��n���������C�ҏv�������Łu�d�v�����������v�ɋL��
�̓��e�ɂ��ďd�v�����������s���܂��B�����Ĕ���l�A����l����
�͏d�v�������������u��́v���u�����v����ꂽ���Ƃ������
���ʂɂď�����������������Ă���܂��B
���̂��Ƃ͑�n��������Ɩ@��R�T���ɋK�肳��Ă���܂��B
�Ǝ҂ɂ��܂��ẮA�d�v����������ӂ�����A���e�ɋ��U����������
�����i�҂ɂ������őΉ������ꍇ���́A�������y�i���e�B�[���Ȃ���
���ꍇ������܂��B�܂�A���蔃���̓����҂̂��q�l�����łȂ��A
���_��O�̏d�v���������͕s���Y�Ǝ҂ɂƂ�܂��Ă��ȗ��ł��Ȃ����
�Ȏ����Ȃ̂ł��B
�悭���N�z�̔���l����́u�����A�C���Ă��邩��E�E�v���Ƃǂ�����
�����Ԃ������Ȃ�܂��ƁA���ʂ����𗣂��Ă��܂���ꍇ������܂�
���A����A���̕s���Y�̎��ɂ��đ�ȏ�L�ڂ��ꂽ���̂ł�����
�u�����ĂȂ������E�E�v�I�Ȗ��𖢑R�ɖh�~���邽�߂ɂ��L�ړ��e��
�����Ȃ�Ȃ��u�p��v�ɂ��ĉ���Ȃ����Ɠ��A�s���ȓ_�͐����҂ɒ��J��
�m�F���āA�������̏�A������������Ă���������Ǝv���܂��B
���A�s���Y�́u�d�v�����������v��s���Y�́u�������v��u�g�㏑�v��
�悤�Ɏv���Ă����������������悤�ł����A�����āu�������v��
�u�g�㏑�v�̂悤�Ɂu���Z�v��u�����v���A�s�[��������̂ł͂���܂���B
�ނ���A�u�@�����Ő������鎖���v��u���̕s���Y�̌��_�v��
��������ƋL�ڂ����������鏑�ʂƂ��l������������Ǝv���܂��B
�����V�����̃e�[�}�́u���Ã}���V�����w���O�`�F�b�N�|�C���g�I�v��\��ł��B
�@�@�@�@�@�@�x���[�K�s���Y�i���j�@�V��
�@2014�N05��02��
<No 29>
�����Q�O�P�S�N�����s���Ȃ��s���Y�I�сE�E�T�����`
�����̃e�[�}�u����łt�o�̌�͂����ƕ|���H�����łt�o���E�E�v
�`�ߖ����̉ˋ�̂��b���ł��`
�Q�O�P�S�N�i�����Q�U�N�j�P�Q���R�P���̑�A���@��P�P���T�W���E�E�E
���̕a�@�̕a���ł́A��قNJŌ�w���u�������l�̗l�Ԃ��E�E�v�Ƃ̘A��
���A�}����A�Ƒ��ŊςĂ����g���̍����^��ɐ�ւ��Ă�������
��l���q�̕v�w�ƁA���̎q���Ō��ݐ��w�Z�Ōo����Ŗ��̕������Ă���
���̂R�l���A�h���̈�t�ƂƂ��Ɂu�����������̎p�v���݂߂Ă����B
�u�R�`�R�`�E�E�v�u�R�`�R�`�E�E�v�x�b�g�e�̑�ɒu���ꂽ�����������
���p�̏������u�����v�̉����Î�̋�ԂɎ�������ł����E�E
�₪�Ĉ�t���y�����C�g�œ��E���m�F���u���ՏI�̂悤�ł��B���S����
�����Q�V�N�P���P���O���Q���ł��v�Ǝ��v�����Ȃ���Ⴂ���ō������B
�u������E�E�v���q�͌Ăт������������͂Ȃ����b�̒��ق������ɂ������B
��t�ƂƂ��ɕ����ɂ����Ō�w���i�[�X�X�e�[�V�����ւ̎��S�A���̂���
�ɕa�����o�悤�Ɠ��������̎��A������t�ɐ����������u�搶�A���������
�̎��S�����͂R�P���̌ߌ�P�P���T�X���ɂȂ�܂��H�v
�ꓯ�u���F�H�v�E�E�E�E�E
�����Q�U�N�S���P���A�l�X�Ə���ŗ����W���ɂȂ�܂����B�X�[�p�[��
�Ɠd�ʔ̓X�A�z�[���Z���^�[���ŁA���܂Őō����z�ő傫���L�ڂ���Ă���
���i���i���A��]���ĐŔ������i���傫���L�ڂ���Ă��āA�W���̐ō��݂�
���z�͂��ׂ̗Ɂi�������~�j�Ə����������Ő\����Ȃ������ɋL�ڂ���Ă�
�邱�ƂɈ�a���������Ă�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�ł��A����łt�o�ɑ����đ����łt�o�i���m�ɂ����ƈꕔ�����j�͕����Q�V
�N�P���P���ȍ~�ɖS���Ȃ�ꂽ������ΏۂƂȂ�܂��B������������ł��B
�����_�̑傫�ȃ|�C���g�́A��Y�ɌW��u��b�T���z�v��������������_
�ł��B�܂�A�����O�ł��Ƒ����Ŕ[�t�̑ΏۂɂȂ�Ȃ��������ł��A����
�����Ŕ[�t�̉\��������Ƃ������ƂȂ̂ł��B
�������O���@�T�O�O�O���~�{�i�P�O�O�O���~�~�@�葊���l�̐��j
���ɔz��҂Ǝq���Q�l�̌v�R�l�������l�̏ꍇ�@�W�O�O�O���~����b�T���z
�������い�@�R�O�O�O���~�{�i�U�O�O���~�~�@�葊���l�̐��j
���ɔz��҂Ǝq���Q�l�̌v�R�l�������l�̏ꍇ�@�S�W�O�O���~����b�T���z
�悤����ɁA������͗a������s���Y�A�L���،��Ȃǂ̍��v���T�C�U�疜�~
�ȏ゠����̏ꍇ�A�����l�̐��ɂ����܂��������Ŕ[�t�́u�Y���Č��v��
���\�Ȃ��Ă��܂��悤�ł��B
����ɗ��������ƁA���Y���Q���~�ȏ�L����̏ꍇ�͉����O�Ɖ�����ł�
�u�P���̈Ⴂ�v�ł����Ă����S���~�̑����Ŋz�̈Ⴂ��������ꍇ�������
���B�܂��ɓ����҂ɂƂ��Ắu�����̋��z���I�v�ƂȂ�܂��B
�ł������_�̒��ŏ��X�ǂ��b���E�E
�����l�������N�҂̏ꍇ�͂Q�O�܂ł̂P�N�ɂ��T���ł�����z��������
�͂U�U�����t�o�ƂȂ��Ă���܂��B��������܂��ƁA�����l���P�T�̏ꍇ
�Q�O�܂ł̂P�N�ɕt�T���ł�����z�������O�̂P�N�U���~�̏ꍇ�͂R�O��
�~�̍T���ł������A������͂P�N�P�O���~�i�U�U���t�o�j�ƂȂ�A�T�O���~
�̊��葝���T��������悤�ɉ����ƂȂ��Ă���܂��B�i�ȁ`�A
�����H�E�E�Ƃ̐����������Ă������ł����E�E�j
�Ƃ���ŁA�u�s���Y�ƎғI�ߐł̃A�h�o�C�X�v��������Ƃ����������܂��ƁA
�u�ǂ������킯���y�n�����͑�R����v�悤�ȏꍇ�A��͂菊�L����s���Y
�̕]�����i����������@��T������悢�̂ł͂Ǝv���܂��B�a�����⊔��
�̗L���،��͑����ł̑Ώۂ̎��Y�Ƃ��Čv�サ�Ȃ���Ȃ�܂��A
�Ⴆ�Γy�n�̏ꍇ�̓A�p�[�g���̑݉Ƃ����Ă邱�Ƃɂ��]���z�����炷
���Ƃ��ł��܂��B�i�������A���Ă�����ǂ��A�����҂����Ȃ��ꍇ�Ȃ�
���X�N������܂��̂ł����ӂ��I�j�����l����ɐ��{������Ȃ̕��X��
�V�z�̃A�p�[�g���̌��z�������邱�Ƃɂ��o�ό��ʂ��������Ƃ��炱��
�悤�ȐŐ��̑[�u���p�����ĂƂ��Ă���̂��Ǝv���܂��B
���A�����͑����ł̂��b�����������Ă��������܂������A�����łɌ��炸
�ŋ��͔��ɕ��G�Ɂu����v��u�����v�A�u��������̌o�ߔN���v���Ȃ�
�W���Ĕ[�t�z�����肢�����܂��B��͂萳�m�ɂ͐Ŗ����̑��k���̕���
�ŗ��m�A�o���m�Ȃǂ̐��̒m���̂�����ɂ����k����邱�Ƃ������߂�
�����܂��B�����k�̎�ԂƔ�p��ɂ���Łu�T���v�ł�����z���T������
���Ŕ[�t���Ă��܂��Ⴊ�悭����悤�ł��̂ł����ӊ肢�܂��B
�����U�����̃e�[�}�́u�_�̏d�v�����������āH�v��\��ł��B
�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x���[�K�s���Y�i���j�V��
�@2014�N04��01��
<No 30>
�����Q�O�P�S�N���@���s���Ȃ��s���Y�I�сE�E�S�����`�@�@
�����̃e�[�}�@�u�Z��̖h�ƃ`�F�b�N�ɂ��āv
�S���ɓ���܂����B����ł��W���̎�����S���P�����炢�悢��X�^�[�g
�������܂����B�����m�̂Ƃ�����{�ł͂S���͓��ʂȌ��ƂȂ�܂��B�V���w�A
�V���ЁA�܂������̉�ЂŐV�N�x�̎��ƌv��̊J�n�̌��ƂȂ�܂��B
����A���������P�N�̓��ł��ߖڂ̃^�C�~���O�̎����ɁA�u���݂��Z�܂���
�Z���v�ɂ��Ă��Ƒ��Łu�h�Ɓv�ɂ��Ă��b��������A���X���ӂ��Ă���
�_����ł���ł����݂��Ɋm�F�������Ă݂Ă͂������ł��傤���H
�����ĉ\�ł�����C�ɂȂ�ӏ��͂ł��邾�����P����Ă݂Ă͂����ł��傤���H
�i���ӊ��N�����ł͉��������A���P�ׂ̈̏o���K�v�Ƃ���ꍇ������܂����E�E�j
�����ŁA�����́u�Z��̖h�ƃ`�F�b�N�v�ɂ��ď������b�����܂��B
���a�̎���́u���{�͐��E�ł��g�b�v�N���X�̈��S�ȍ��v�ƌ����Ă܂����B
�ł��A�c�O�Ȃ���u�J���������v�����C�Ȏ���́A�s��Ɍ��炸�n���ł�
�ߋ��̗ǂ�����̘b�ƂȂ��Ă��Ă���܂��B
�ܘ_�A�u�S�z�����n�߂��炫�肪�Ȃ��I�v����������܂��A�Ƒ��Łu�h�Ɓv
�̎��ɂ��Ĉ�x�b�����邱�Ƃɂ��A�u�C�t���Ȃ��������v���u�����v�ł�
�u���ӂ���ӎ��v�����܂�A�u���ւ̌��͕߂�����ǂ��A���r���O�̃T�b�V��
���͊J�����܂܂ŋߏ��ɔ������ɏo�����Ă��܂��E�E�v����
�u�h�Ƃ̏����̏����v�̃~�X�Ȃǂ��Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂��B
�Ƃ���ŁA���͎d������u�h�Ƃ̎��ɂ��ďڂ������v����b�����@�
�悭����܂��B
����͏Z���ЂɂĂ��q�l�̑O�Łu�h�Ƃ̃Z�~�i�[�v������Ă��������
���b���f���܂����B���x����Ђ̕���ی���Ђ̕���������X�u�h�Ɓv��
���b���f���܂��B�����̕��X�̂��b�̒��ł悭���ʂ���_���R����܂�
�̂ł��Љ�܂��B
��́A�u���ӂ͂��߂��邱�Ƃ͖����v�Ƃ����_�B
�Q�ڂ́A�u�p�����厖�v�Ƃ����_�B
�R�ڂ́A�u�ߐM�͋֕��v�Ƃ����_�ł��B���Q�l�܂łɁE�E
���A�������Ƃ������܂��ăp�\�R����X�}�[�g�t�H���A�^�u���b�g�ɂ�
�u�h�ƃ`�F�b�N�v�ƌ����������܂��ƌ��x�@���i�L�����j�⑊�n�x�@��
�i�������j���쐬�������܂������ƒ�ł́u�h�ƃ`�F�b�N���X�g�\�v������
���������A���ڂ��Ƃɂ����g�̏Z�����`�F�b�N�m�F���邱�Ƃ��ł��܂��B
���������p���Đ���A���̋@��Ɂu�����g�Ń`�F�b�N�f�f�v���Ă݂Ă�
�������ł��傤���H
�����T�����̃e�[�}�́u����łt�o�̌�͂����ƕ|���H�����łt�o���E�E�v
��\��ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x���[�K�s���Y������Ё@�V��